また今日もあのセリフを他の教員から聞く。
「後半、学生たちの集中力がなくなってきました」
日本語教育の現場では、学生の集中力ややる気について議論されることがよくある(わたしが勤める日本語学校だけかもしれないが)。特に長時間にわたる授業では、後半になると学生たちの集中力が切れることが課題として挙げられる(わたしが勤める日本語学校だけかもしれないが)。この記事では、「学生の集中力がなくなる原因」と、それに対する考え方や対策について考察していく。
集中力が切れるのはなぜ?授業スケジュールと学生の状態
わたしが担当するクラスは、朝9時から12時までの3時間、週5日間の授業がある。1日4コマに分かれており、漢字、語彙、文法、読解、聴解など、多岐にわたる内容を学んでいく。授業の後半、具体的には3限目や4限目にあたる時間帯に学生の集中力が切れることが指摘されている。
授業の合間には、5分間の休憩時間が設けられているが、果たしてこれだけで集中力をリセットすることが可能なのであろうか。
一般的に、人間の集中力は45分が限界とも言われている。このような条件下で、学生たちが集中力を維持するのは非常に難しいと思われる。
学生の興味と授業の関連性
集中力を維持できるのは、自分が好きなことや興味のあることに限られる場合が多い。漢字や語彙、文法、読解、聴解といったすべての分野に興味を持ち、楽しめる学生がどれほどいるであろうか。
この点を踏まえると、「学生の集中力がなくなった」と指摘するのは、学生に興味を持たせられなかった授業設計や内容に問題があると言えるかもしれません。教育者として、この課題をどのように克服すべきかを考える必要がある。
学生のやる気を引き出すための工夫
集中力の問題を「やる気の低下」と捉え直すことで、改善の糸口が見えてきた。以下は、学生のやる気を引き出すための具体的なアイデアである。
- アクティブな学習活動を取り入れる: ペアワークやグループディスカッションで、学生同士が学び合う機会を設ける。
- 興味に基づいた教材を活用する: 学生が興味を持ちやすいトピック(例: 日本の文化やアニメ)を取り入れる。
- 適切な休憩とリフレッシュ方法を提案する: 5分間の休憩で、ストレッチや軽い運動を促す。
教員としての視点を見直す
最後に、教員として「学生の集中力が切れた」と簡単に言わず、「学生のやる気を高められなかった点は何だったのか」と振り返る姿勢が大切であると思う。この視点の変化が、授業内容や進め方を改善する大きなヒントになりそうである。

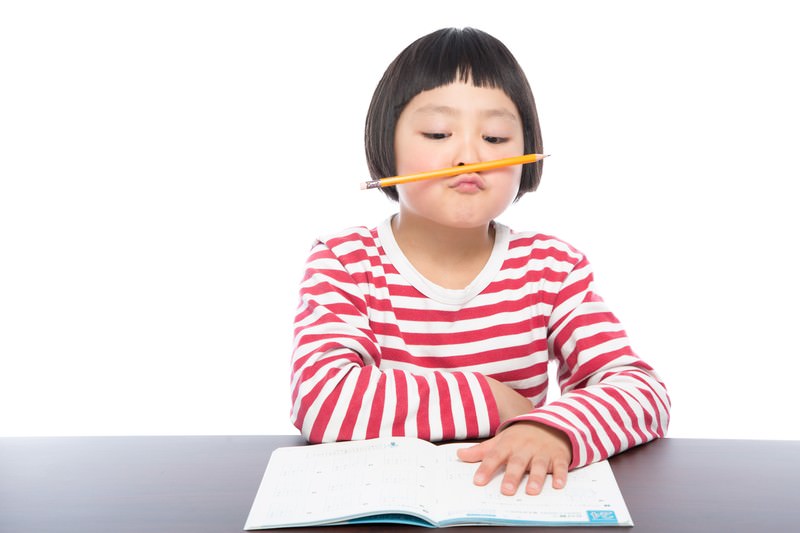

コメントを残す